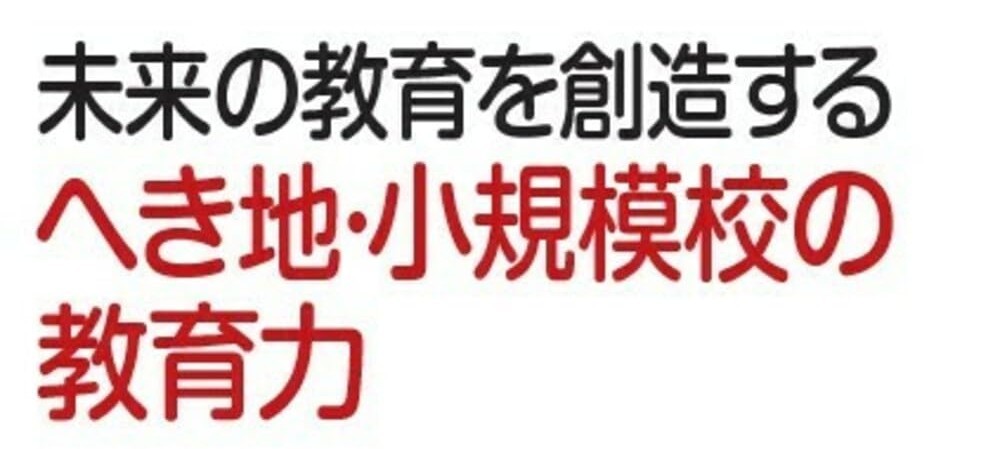某篠山の小学校の統合などについて、ご相談を受けました。
いろんな話の中で意見を述べさていただきました。
私はそこに住まれている方々の思いが一番だと思っていますが、今のこの〇〇小学校などは小規模校の域を超えた小学校ではあると思っています。
子どもたちの教育的視点で考えると、小規模校は先生方全員が子どもたち全員にかかわることができる素敵な面と、学力向上には適していると思います
しかし反面、社会性や競争する場面の少なさの課題や、学校行事や地域との連携事業でのさみしさなど、地域交流に大きな影響を与えるとは思います。
ただ、私が常々市の教育委員会に意見している、ICTを使った授業の市内全体への方向性や、西紀地区3校のICTを使った交流などを中心に行うことができれば、その地区いながら最先端の学びを提供できる学校ができるとは思っています。
地域の宝である学校を失いたくない方々と、統廃合して活気ある学校生活をと考える意見があることは存じ上げており、私個人としては、どちらにも対応できる方向性を見出していくのが必要だと考えており、お答えになっているかは定かではないですが、どちらの方向性でも、子どもたちがしっかり学べるように、しっかり繋がりをもっていけるように、今のままではなく、ICTで交流したりし、繋がりを大きく深めていくことは必要だと思っています。
ICTの交流とは、全国的に統廃合が進む中で、交流ができない地域と大きな学校とを画面上でつなぎ(100インチなどの大画面で)そこで一緒に授業を受けることができるスタイルです。
これなら今の丹波篠山でも導入可能だと思っています。
もちろん体育や行事の課題は残っていきますが、今のままで行っていくのであれば、そういう対応も時代の流れとともにできるとは思います。
統廃合は今のまま放っておくと必要になってきますが、まだまだできることはたくさんあると思っています。そうすることで人口が少ない地域にも住みたいという人が出てくるでしょうし、過疎化していっている丹波篠山の課題にも一部対応が可能だと思っており、これが今の段階でできる私の強い思いではあります。

ちなみに今日から面白い登校をする子が丹波市にいました。 小規模特認校、こんな制度ができています。
小規模特認校とは、小規模な学校でありながら、その特色ある教育活動や豊かな自然環境などを活かし、通学区域外からも児童・生徒の入学を認める制度によって指定された学校のことです。
より具体的に説明すると、以下の点が挙げられます。
目的は、小規模校の活性化 都市部の子供たちに豊かな自然環境での教育機会を提供し、少人数教育のメリットを活かしたきめ細やかな指導 学校の特色づくりや複式学級の解消も場合によってはある可能性があります。
特徴として、通学区域外からの入学が可能であり、通常の学校は居住地によって通学区域が定められていますが、小規模特認校は一定の条件のもと、区域外からの入学が認められます。
特色ある教育活動とは、自然体験学習、地域との連携、国際交流、特定の教科に力を入れるなど、学校ごとに特色のある教育が行われているようです。
少人数教育として、児童・生徒数が少ないため、教員一人ひとりの目が届きやすく、個別指導やきめ細かいサポートが期待できます。
入学の条件は、小規模特認校の教育方針に賛同し、協力できること 保護者の責任と負担で安全に通学できることで、基本送迎が必要になってきます。
また原則として卒業まで通学する意思があること
メリットは児童・生徒が、きめ細やかな指導、豊かな自然の中での学習、特色ある教育を受けられる、新たな人間関係を築けること。
児童・生徒数の増加による活性化、特色を活かした学校運営や子どもの希望や特性に合わせた学校選択の機会が増えること。
小規模特認校制度は、少子化が進む地域において、学校の存続や教育の質の維持向上を図るための有効な手段の一つとして注目されています。
制度の詳細は自治体や学校によって異なるため、関心のある場合は各自治体の教育委員会や学校に問い合わせる必要がありますが、丹波篠山市で小規模特認校制度はありません。
篠山はまだですが、丹波市の子どもが西脇の小規模特認校に通うことになった例がこの4月からあります。 そういう流れを作ると、篠山の小学校も形は変わってくると思います。
統廃合だけが今後の少子化の方向性ではないことを、しっかり皆さんにお伝えしていきたいと思います。